2025.08.31
コラム第32回「いざというときに備える!司法書士が教える生前対策7選」
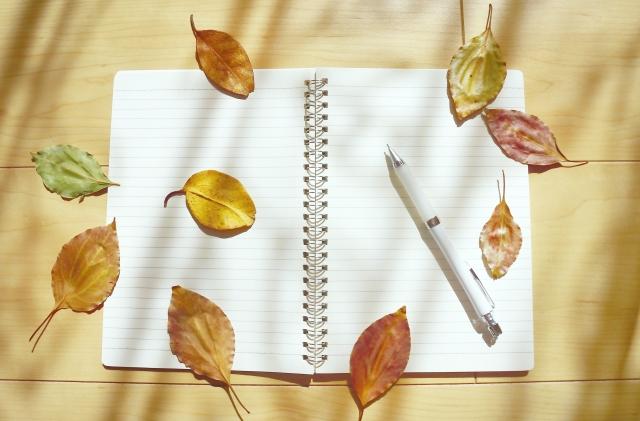
「まだ大丈夫」と思っているうちに、ある日突然、事故にあったり、病気になってしまう。相続が発生してしまい、家族が遺産を巡ってトラブルに。 そんな不幸を防ぐには、元気がある今のうちに備えておくことが何より大切です。今回は、司法書士の視点から「元気なうちにやっておくべき生前対策7選」をご紹介します。
1. エンディングノートで意思を記録する
生前対策や終活と聞くと、よく浮かぶ「エンディングノート」。医療や介護、葬儀の希望、財産の所在や連絡先まで、書き残しておくことで家族が迷わず行動できます。形式の決まりはありませんが、法的効力はないため、重要事項は遺言書と併せて準備しましょう。
2.遺言を作成する
生前対策や終活と聞いて、エンディングノートと同じくらい思い浮かべることが多い「遺言」。相続が発生した時にもめる原因は、やはり遺産の分け方です。遺言を書いておけば、誰にどの財産を引き継いでほしいか意思表示を書き残すことができます。
3. 相続税のシミュレーションで分け方を決める
相続税額や納税方法を事前に把握しておくことで、相続発生後の混乱や納税資金不足を防げます。家族構成や財産の種類に応じて試算し、誰に何を相続させるか、分け方の大枠を決めておくと安心です。
4. 生前贈与や保険の活用
相続税額がわかったら、次は税金対策をしていきましょう。よく聞かれるのは「生前贈与」でしょうか?年間110万円までの贈与は非課税ですが、2024年の税制改正で持ち戻し期間が延長されています。
また、生命保険や医療保険を活用することで、相続税対策や葬儀費用の確保、医療費への備えが可能になります。
5. 家族信託を活用する
将来の財産管理を信頼できる家族に託せる制度です。不動産や預金を信託しておけば、認知症発症後も売却や運用などがスムーズに行えます。
6. 負動産の整理と資産の活用
利用予定のない土地、山林や畑などや管理が難しい建物は、売却や寄付などで早めに処分を検討しましょう。売却ができるタイミングが出てきても、認知症になっていると売れなくなってしまいます。
遊休地なども、何もしないのはもったいない。よりよく活用も視野に入れましょう。
生活の充実も「生前対策」
このあたりは、生前対策や終活としてよく聞くと思います。ただ、これだけではないです。
相続後のトラブルは財産をどう分けるかです。その財産が残ってしまうのが問題で、みなさんの財産はみなさんのためのものです。そこで「しっかり」使うというのも、忘れやすいのですが、生前対策です。
7. 旅行に行く、美味しいものを食べるなど、人生を楽しむ
みなさんの持つお金はみなさんのために使うことです。ただ、「お金を使う」のも元気じゃないとできません。行きたかった場所への旅行や、気になるレストランや思い出の味を家族と楽しむことも、立派な生前対策です。
まとめ
生前対策は財産や制度の準備だけではありません。人生をどう締めくくりたいかを考え、そのために動くことも重要です。これらあげたことは、全て元気な時ではないとできないものです。ただ、全てをやったからいいというわけではありません。みなさんの家族状況や財産状況に応じて、「すべき対策」と「しなくてもよい対策」は違います。
遺言や家族信託などをはじめ、不動産整理などは客観的な視点も大切です。身近な専門家の意見をもとに進めていくとよいでしょう。私たちは、ライフプラン全体を見据えたご相談も承っています。ぜひお気軽にご連絡ください。
執筆 司法書士法人ファミリア
ファミリアグループサイトはこちら



