2024.12.31
コラム第16回「公正証書遺言ってなに?」
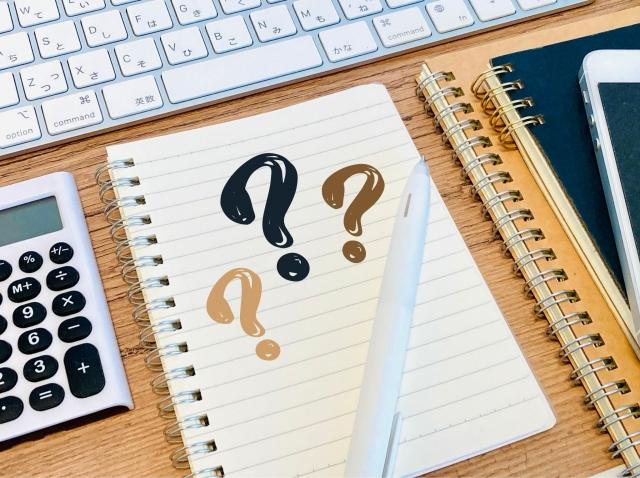
将来の相続に備えて遺言書を遺される方は多くいらっしゃいます。一口に遺言書といっても、実はいろいろな種類があって、大きく分けて①公正証書遺言②自筆証書遺言③秘密証書遺言、の3種類があります。
それぞれの違いと特徴は次のようになります。
まず、公正証書遺言は、公証人と証人の立会いのもとで公証役場で遺言書を作成、原本保管されるものです。この際、遺言者はその全文の手書きは必要ありません。
次に、自筆証書遺言です。これは、遺言者自身で自筆し、遺言者自身もしくは特定の方式で法務局で保管されるものです。財産の目録を除き、基本、遺言者が全文を手書きする必要があります。
最後に、秘密証書遺言とは、遺言者が証書を封じ、公証人と証人に自己の遺言書であることを申述し自己で保管するものです。
上記の通り、遺言書はその作成方法により種類が分かれるものですが、いずれにせよ、共通して言えるのは、遺言とは、遺言者が亡くなった後、その意思を実現するために遺すものです。そのために、その意思の実現に間違いがないよう、法律によって厳格にその方式が定められています。法律に定められた様式に則って初めて「有効な」遺言となるのです。逆に言えば、法律に定められた様式から外れてしまっては、その遺言は「無効」となります。
亡くなった方が、せっかく次の世代の方のために遺した遺言が、想いはあるのに法律様式から外れてしまっているがために無効とされるのは、遺す方にも遺される方にも不幸なことです。
また、遺言については保管についても注意が必要となります。
せっかく遺言書を遺されていても、火事や地震などによりその遺言書が紛失してしまっては、故人の遺志を知るすべはなくなってしまうからです。
また、保管に関連することですが、遺言書の偽造や変造にも注意が必要です。例えば家のタンスに入れていた遺言を、相続人が勝手に書き換えてしまうことも、可能性がないわけではありません。そのため、その遺言書の内容を明確にするために、家庭裁判所による「検認」という手続きが必要となります。
以上のように、遺言は「法律に定められた様式に従って記述し」、「紛失や偽造・変造がないようにきちんと保管」されることが必要です。
もちろん、最終的には遺言者の意思によるものなので強制されるものではないのですが、上記の懸念点を払拭し、遺言としての大切な条件を満たすため、「公正証書遺言」によって遺言を遺されることをお勧めします。
公正証書遺言のメリットとして次のようなものが挙げられます。
まず、公証人という法律のエキスパートが作成しますので法的不備という心配はありません。
また、公正証書遺言は公証役場での保管がなされます。そのため、紛失、偽造等の心配はなく、家庭裁判所による検認作業も不要となり、すみやかな遺言内容の実現が可能となります。
さらに、例えば、自筆証書遺言では原則自筆が必要ですが、これもご高齢で手先が不自由な方には困難を伴うものです。その点、公正証書遺言については、本文はもちろん、署名についても、病気等の理由があれば代替措置が可能となります。
もちろん、専門家が携わるため、自筆証書遺言と比べて費用がかかるという面はありますが、遺言書は文字通り一生に一度の大切なご家族へのお手紙でもあります。ぜひ、そのお手紙が言い回しの違いや不注意によって台無しになってしまうことがないように、遺言を書かれる際には専門家にご相談いただければと思います。
執筆 司法書士法人ファミリア
ファミリアグループサイトはこちら



